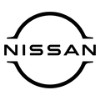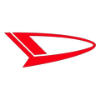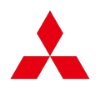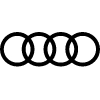警告灯点灯 原因を解決する方法

POINT
- エンジン警告灯とはエンジン内部の故障をセンサーで感知して警告を促すもの
- エンジン警告灯には赤色と黄色がある。赤色は運転が危険な状態で、黄色は注意が必要
- エンジンの故障箇所を点検
- 修理するとエンジン警告灯は消える
【原因】エンジン警告灯の色による意味の違い
エンジン警告灯(エンジンチェックランプとも呼ばれます)はエンジンに何かしらの異常が発生した場合、センサーが異常を感知して点灯します。
また、機器の故障だけでなく、故障を感知するセンサー自体に不具合が発生した場合にもエンジン警告灯が点灯します。
エンジン警告灯は運転席のメーターパネルの中にあり、異常がある場合はエンジンがかかると点灯し、エンジンを切ると消えます。
警告灯の色には赤色と黄色があり、赤色の場合はそのまま運転するのは危険ですので、ただちに走行を中止し、速やかな点検・修理が必要となります。黄色の場合は走行に注意が必要で、なるべく早く点検・修理に入れることをおすすめします。
エンジン警告灯の点灯を引き起こす原因は非常に多く、また複数の故障が原因となっている場合もあります。点灯したまま放置すると故障箇所の症状が悪化し、修理費用が高額化することもあるので、速やかに整備工場へクルマを持って行きましょう。
【問題解決】このパーツが故障するとエンジン警告灯が点灯する
エンジン警告灯は、Vベルト、エンジンECU、イグニッションコイル、O2センサー、エアフロセンサーなどの不具合で点灯することが多いようです。
Vベルトは、エンジンの回転力を動力としてオルタネーターや冷却ファンなどに伝えるゴム製のベルトです。
エンジンECUは、エンジンの制御を行うコンピューターユニットのことです。
イグニッションコイルは、燃焼室内の圧縮した空気とガソリンの混合気に着火するスパークプラグに高い電圧をかけるためのパーツです。
O2センサーは排気ガス中の酸素濃度を測定し、その情報を元にエンジンECUが混合気の濃い・薄いを判定し燃料の供給量を決定します。ラムダセンサーも同様の働きをしますがさらに細かい情報をECUに送ることができます。
エアフロメーターは、エンジンが吸い込む空気の量を計るための部品で、エアフロ、エアフロセンサー、エアマス、エアマスセンサーと呼ばれる場合もあります。そのデータなどを基に、ECU(エンジンコントロールユニット)が最適な燃料の量をエンジンに供給しています。
これらの寿命は車種によっても異なりますが、おおよそ10年・10万kmほどです。中には5〜6万kmほどで故障が出始めるケースもあります。故障箇所を修理し、テスター(診断機)によって記録をリセットするとエンジン警告灯は消えます(消えない場合は故障箇所が他にもある可能性があります)。
エンジン警告灯は不具合を早期に知らせる重要なパーツです。ここでは代表的な故障原因を挙げましたが、エンジン警告灯が点灯する原因は他にも多数考えられます。これらの故障の中には、放置していると走行不能になるだけでなく、最悪の場合は高額な費用がかかる故障につながるケースもあります。まずは警告灯点灯の原因を特定するために整備工場へ持ち込み、テスター(診断機)で故障コードから判断するのが確実です。
(山崎 龍)
エンジンの不具合は重大事故の要因にも!?
技術力の高い修理工場に早めに修理を依頼しておくことで、
結果として安く済む可能性が高いです。
カープレミアガレージは東証プライム上場企業のプレミア
グループが厳しい基準で加入している安心できるお店です。